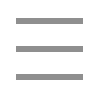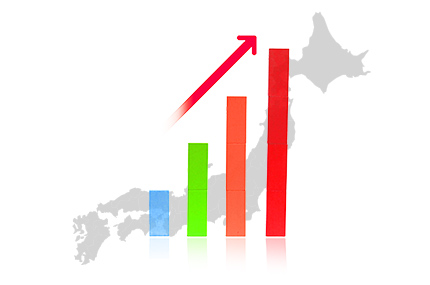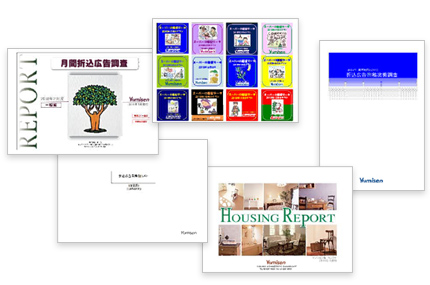<第二回:信用できるのは、どっち?>
――「信頼性」という意味で、紙とデジタルの違いはありますか?
笠原)WEB広告の良さは、値段等を間違った時、すぐに訂正できること(笑)。紙だとそうはいかないから、一旦、刷ったものが配られてしまうと取り返しがつかなくなる。
一方で、簡単に書き換えられるWEBのものは、ひょっとすると偽物だという可能性もある。そういう点では、紙の信頼性は高い。
ただ、情報を蓄積していくという点では、紙のチラシだと、いちいちめくっていかないといけないが、デジタルならすぐに検索できる。値段もすぐに分かるので便利。
――実際、消費者の方がデジタルの情報を疑っている、ということはありますか?書き換え可能な情報という意味で。
湯尾)結局、デジタルは一般的になりすぎて、おっしゃるように、いつでも情報が書き換えられるので、僕はあまり信用していない。僕が言うのもどうかとは思いますが(笑)。
デジタルは、信用力がありそうでない。だからこそ、紙やアナログの方が正確かなと。実際、僕自身、数年前に家を買った時も、デジタルで色々な物件情報も調べましたが、最終的には住んでいる地区の折込チラシを見た方が安心したし、信頼できた。デジタルは書き換えも含めて、いつ、どのように情報が変えられるか分からない、という変な不安に駆られる。だから「信頼性」という意味では、今はまだ「一周回ってアナログ」なのかなと。
――いろんなサイトで皆さん、情報を参考にされるかと思うのですが、口コミすらもフェイクや仕込みが混じっているのではないかと。
湯尾)ありますよね、正直。どんなサイトでもあると思います。
――アナログだと、そういう「ウソ」を組み込みづらい?
笠原)まずその前に、チラシなどアナログ媒体には口コミがあまり載らない。だから評判を知るには、デジタルが向いている。でも「やらせ」も混じっている。通販サイトのブラックフライデーのセールで物を買う時には、その口コミが「さくら」かどうか、チェックに掛けています。それも本当に正しいかどうかはわからないけれど、後ろ盾があるだけましかなと。
――さくらチェッカー、よく使われるんですか(笑)。
笠原)よく使いますね。
湯尾)デジタルは短期決戦。結局、そのブラックフライデーってトップページに広告が載っていたら、そのページもしくは、関係しているページ全てが安いかのような印象が刷り込まれる。実はブラックフライデーだけども安くなっていない商品とかもある。
――今や、消費者や生活者に疑われていることを前提に社会が動いている。そういった「賢い」生活者の方々を相手にする時に、メディアの発信側としては、どういったことに留意してビジネスをされていますか。
湯尾)弊社で言うと、デジタルの良さは前面に出すが、デジタル一辺倒にすることは絶対にない。デジタルとアナログの体験、僕は「融合」と呼んでいますが、今はデジタル時代の到来とともに「デジタルだけが優れているよね」という段階から、一周回ってアナログの良さも取り入れつつ、アナログとデジタルの良さを融合させる体験をどうやって作っていけばいいのかを考えているところです。デジタルとアナログ双方の本来の良さをそれぞれ発揮して新しい体験を作っていく、ということを意識しています。
笠原)紙は形として残ってしまうだけに、リリース前の校正・校閲が厳しい。会社として最も留意しているのは「人を傷つけない」「公平性を持つ」という視点と、人権への配慮。
――新聞社や出版社には校閲部という部署があって、プリントメディアを扱う会社はそこに非常に力を入れている。一方で、WEBマガジンを発行している会社で校閲部なんて聞いたことが無い。WEBのニュースなんて、誤字脱字のオンパレード。
湯尾)校閲という仕組み自体が存在しない。スピード勝負なので。ある意味、メディアを含めて、悪い意味で最適化されすぎている。おっしゃる通り、誤字脱字が多い。
デジタルはいくらでも書き換えができるから、そこが良いところでも悪いところでもある。誤字が見つかったり指摘されたら、その場ですぐに修正できる。それが当たり前になっている状況。
笠原)情報に対して「お金を払う」とか「払わなくていい」という価値の違いもあるのかな。

撮影場所: WeWork 御堂筋フロンティア 共用エリア
~第三回へ続く~