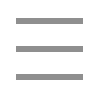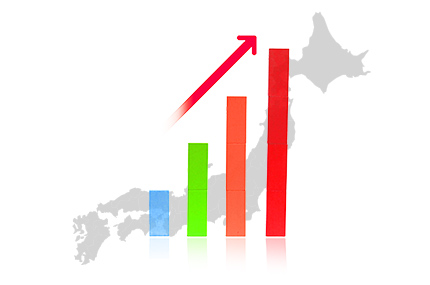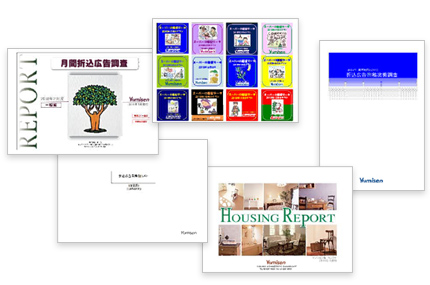<第五回:アナログがなくなる日>
――デジタルとアナログの使い分けをするにあたって、我々広告会社はクライアントさんの要望に応じて様々なアイデアを考えていかなければならないのですが、お二人が普段生活されている中で、アイデアを出す為に気にかけていることなどがあればお聞かせください。
湯尾)デジタル領域では、ITやテクのことだけを知っていればいいみたいに思われがちだが、そうではない。僕自身は、先ほどの「融合」という話と一緒で、実生活の中でどれだけITやDXが浸透しているかを見ています。回転寿司チェーン店に行かれたら分かると思いますが、シンプルに人と会わずして高い満足度が得られる。要はスマホ一つで予約をしてQRコードを店舗でかざし、そのまま人に会わずに着席し、メニューもスマホやディスプレイで注文して、ご飯が運ばれてきて食べ、そしてお会計はQRコードさえかざせば、人を介在せずして終わる。でも、満足度は高い。こういう体験を作ろうとしたら、デジタルの世界だけではダメなんです。リアルな体験、アナログの体験などがないと、そういうアイデアは出てこない。だから、リアルとかアナログの体験はかなり重要視しています。
笠原)ネットサーフィンばかりしていると自分の興味ある話題にしか目がいかなくなってしまうので、私の場合は違うところに行こうと思って、よく百貨店に出かけます。いわゆる○○展のような催事。瀬戸内寂聴展に興味はなかったけれど、無料で入れる権利があったからと行ってみたら、結構面白かった。そういう体験があったりすると思わぬインスピレーションが得られたり、自分の幅が広がったりする気がします。先ほどの回転寿司の話にも近いのですが、「この物事はどうして起きているのだろう」と考えてしまうこと。最近でいうとスーパーで売っている「カット野菜」が気になる。割高なんですが、よく言えば「SDGsに繋がるんじゃないか」と。少々形が悪いとか傷があっても、切ってしまったら分からない。元が安いから、お店は儲かるし廃棄もなくなる。食べる側からしたら、清潔で衛生的で鮮度があったらいいのではないか、といったようなことを妄想する。
あとは、テレビドラマやバラエティー番組を見るのですが、昨日もTVerで「パリピ孔明」を1.75倍速で見てたんですけど、音楽をテーマにしたドラマなので、さすがに音楽を1.75倍速にしたらダメ。こんな風にいい加減な行動をしておきながら、そのおかげで大切なことに気づく。
――そういう行動がアイデアに繋がる?
笠原)繋がるかもしれないし、繋がらないかもしれない(笑)。
――最後に、プリントメディア全般も含め、アナログ媒体は今後どうなっていくと思われますか?
笠原)紙は紙で、昔で言うところの情報革命の一つではあったので、印刷やコピーの需要がある限り、無くなることはないと思います。ただ、やはり「蓄積していくもの」はデジタル化、その場限りのものや、すぐに手に取りたいものはこういう紙にして、使い分けの時代になっていくのではないかと。もっと社会が成長して、受け手側が発信者側に応じて選ぶ。例えばテレビが始まった時、テレビは音・音声も電波で流すものだから、本来ならラジオと一緒みたいなものですが、ラジオは運転しながらでも聞けるが、テレビはダメ。そうした時に消費者や社会全体が使い分けしていく時代になってほしいなと思います。
湯尾)僕もアナログは絶対に無くならないと考えています。ずっと申し上げている通り、デジタルとアナログを融合する体験を作り出していかないといけない。デジタルはデジタル、アナログはアナログ、となっているのが今の状況。そうではなくて、それぞれの良いところを補完し合っていくのが必要なのではないかなと。
ただ、もしかしたら、全員がタブレットを持って通信できるようになっていて、かつ、スムーズにPDFみたいなものを共有できるような仕組みが出来たら、紙やアナログは無くなるかもしれないです。しかし、絶対にあり得ないので、なるべく融合とういうのを考えてやっていく世の中になるのではないかなと思います。

撮影場所: WeWork 御堂筋フロンティア 共用エリア
(終わり)