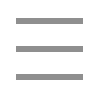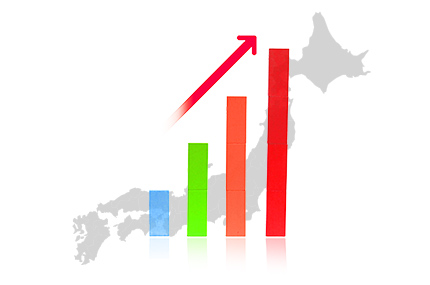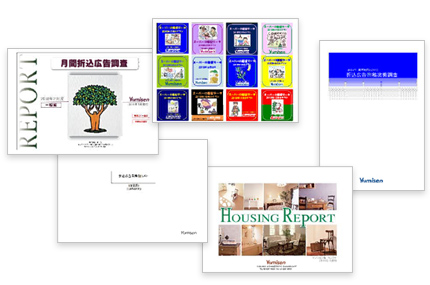<第四回:デジタルの限界から一周回ってアナログ>
――とはいえ、最近はデジタルにも限界が見え始めた。勘のいい企業は、すでにデジタル偏重の弊害や行き詰まりを感じ始めているようですが。
笠原)コロナがだいぶ落ち着いた頃、当時私は東京で単身赴任をしていたのですが、単身者が多いマンションにフードデリバリーのハガキサイズのチラシがポスティングされていました。フードデリバリーなんて、WEBで申し込むものなのに。そのハガキには「初回2,000円オフ」って書いてあって、「なるほど、そういうことか」と。例えば、大してお腹が空いていない時間にWEBでフードデリバリーの広告を見ても何とも思わず終わっていたところが、夕方ぐらいにチラシやハガキが机の上に置かれてあるのを見たら「これなんだよね」となる。
――夜、帰宅して、ポストにフードデリバリーのチラシが入っていたら「注文しようかな」って思いますもんね。
笠原)例えば、飲んで帰ってきた時に見かけて「こんなもん要らんわ」って思っていたチラシでも、翌日になって改めて見てみると、昨日と同じものなのに、意外と興味がわいてきたりする。
湯尾)おっしゃる通り、デジタルは今、限界を迎えています。当たり前のようにスマホ画面を見ていて、たまたまタイミングが合えば、先ほどの笠原さんのような体験はデジタルでも可能だと思います。しかし、四六時中スマホを握っていても、自分が求めていたタイミングでフードデリバリーの広告が出てくるかと言えば、そこは分からない。出てくるかもしれないし、出てこないかもしれない。ただ、アナログだったら、そこに物体があるので、目に入る確率は高くなる。それがデジタルだったら、ある意味、抽選でたまたま当たったという感じになる。デジタルの技術を使ってコントロールはしているが、アナログだとそもそもコントロールしなくても目の前にあるので、やはりそこはデジタルがまだまだかなと。もちろんAIの技術もあるのでどんどん改善されてはいくでしょうが、実際の体験で置き換えると限界を迎えているので、デジタルとアナログを融合させない限り難しいと思っています。
結局、これだけデジタルが流行り、電子書籍も流行っている中で、ふと自分が面白いなと思った本なら全巻所有してみたくなって、アナログに戻る。デジタルが行くところまで行ったら最終的にはアナログに戻ってくる。このサイクルがどんどん回って質の高いものになっていくのではないかな。
――笠原さんはデジタルの限界やアナログの限界を感じますか?
笠原)記録媒体の発達でいうと、昔はトランジスタ、次が磁気テープ、ハードディスク、CDという光媒体に発展しました。けれども、皆さんのパソコンの記録媒体はSSDが主流になりつつあるということでトランジスタに戻っている。某ECサイトのデータセンターはテープも使い始めていて、このように記録媒体は戻っている。私たちはものごとはどんどんまっすぐ進むイメージをしているが、戻ってきたり回ったりしている。そんな感じで、湯尾さんの話にもありましたが、漫画を読んでいると紙じゃなきゃダメだ、ということになって、家の本棚は漫画一色になるというような。
湯尾)僕の持っている携帯も、結局は手帖。太いですし、戻るんです。昔は僕も紙の手帖使っていましたし、やっていることは同じなんです。それが形を変え、デジタルになっただけなので、結局、戻ってくる。
――進化が一直線上にいかない?
笠原)最近、駅から紙の時刻表が消えました。「QRコードを読み込んで下さい」とのこと。さすがに「それはちょっと違うでしょ」とは思っていますが、どうせまた戻ってくるはず。DXって、鉄道会社が駅から時刻表を外すようなおかしな方向にいってしまう。にもかかわらず、それが受け入れられてしまう。駅でパッと見てすぐに分かるように、B4版とかB3版の時刻表を貼っといてくださいよ、コピー用紙でいいから。それくらいならばそんなにコストがかからないでしょと思う。

撮影場所: WeWork 御堂筋フロンティア 共用エリア
――DXを進められている側としてはどうですか。
湯尾)おっしゃる通りで、確かにQRコードで見られたら便利ですけど、わざわざスマホをかざして読み・見る、その間に何秒かかるのか。その面倒臭さがある。そこは果たしてDXが必要かというと、そうではない。利便性が失われている。
笠原)QRコードで見に行って時間をロスする。タイパが悪い。紙だとすぐ見られるのに。今の若い子はすぐにタイパって言うし、スマホの方が早いと信じきっている。電車が来る時間をスマホで調べる。
広告会社や企業のような発信者側は、自分たちが払う金やコストばかり考えているけれど、受け手側のコストはどうなのか。
湯尾)最適化されすぎているがために見えなくなっていますが、受け手のコストって確かにある。スマホでなんでもできる世の中になった反面、逆に面倒臭くなっている。皆さんスマホにメモを書きますが、どう考えたって紙に書く方が早い。
――アプリが立ち上がるのを待つより、紙の方が早い。
湯尾)そうです。ここもバランスですよね。難しいけれど。
笠原)電気や電波が通じないシチュエーションもある。今年、出張時に東京ドームホテルに泊まったのですが、チェックインする際に画面を見せてくださいって言われたのですが、電波が全然通じないためにスマホの画面が開かない。たまたま隣の東京ドームでアイドルグループのコンサートをやっていて、入場が電子チケットだったらしく、みんな一斉に電波を使うもんだから、一時的に繋がらなくなっていた。デジタルでは、往々にしてこういうことが起こる。
湯尾)似たような話だと、デジタルスタンプ。今まで紙にスタンプしていたのがアプリに置き変わりました。店舗からすれば、いちいち押さなくていい便利さがあるものの、これまた良い面と悪い面があって、それこそ繋がらなかったら使えない。せっかくスタンプが貯まっていくのに使えないなんて、ユーザーからすれば機会損失ですからね。
~第五回へ続く~