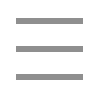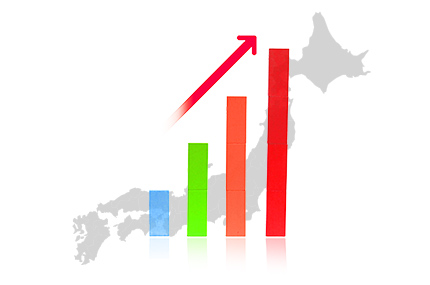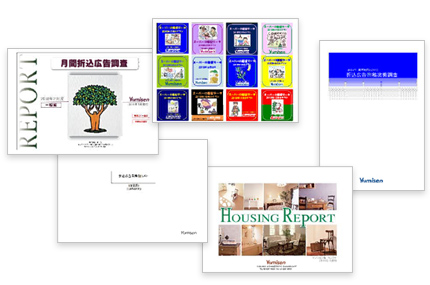寒さもひとしお身にしみるころ
年の瀬も押し迫ってまいりました。
ということで、
まずはサンタクロースのお話から。
サンタクロースの起源は、
子どもたちの守護聖人といわれる
セント・ニコラスだということはご存じでしょう。
セント・ニコラスは、ローマ帝国時代の4世紀の初め頃、
現在のトルコ共和国にあたる場所に住んでいたカトリックの司教です。
この司教は大の子ども好きで、生涯を慈善事業に尽くしたことから、
後に守護聖人として崇められるようになりました。
貧しい子どもたちにプレゼントを贈るという司教の行動が、
現在のクリスマス・プレゼントの始まりだとも言われています。
では、みなさんの思い描くサンタクロースってどんなイメージですか?
大きな身体にまぁるいお腹、白いひげを豊かにたくわえ、
真っ赤な衣装に身を包んだ、赤ら顔のおじいさん。
おおむねこんな感じじゃないでしょうか?
でも、実は20世紀の初めのころまで、
サンタクロースには統一されたイメージはなかったそうです。
〝クリスマスの前のよる〟などの絵本で知られる
アメリカの詩人クレメント・C・ムーアは詩の中で、
「サンタクロースは大きな顔で丸い小さなおなか、
元気いっぱいで陽気な、小さな妖精の太っちょおじさん」
というふうに書いています。
当時の画家たちはこの詩をヒントに
サンタクロースの姿を思い思いに描いていきました。
描かれた姿のほとんどは小さな妖精のようで、
太っていたり、痩せていたり、
衣装の色も白、青、緑とさまざまでした。
誕生から1500年以上、
サンタクロースには共通するイメージがなかったのですね。
この人気者サンタクロースに目をつけたのがコカ・コーラ社でした。
クリスマス・キャンペーンにサンタクロースを起用したのです。
同社は広告用のサンタクロースのイラストを
シカゴ育ちのハッドン・サンドブロムに依頼します。
1作あたりの報酬は$1,000。
当時は自動車の値段が$700ほどだったらしいので、
相当高額なギャラですね。
コカ・コーラ社は、
それほどこのキャンペーンにかけていたのでしょう。
意気込みが感じられます。
そのようにしてついにサンドブロムによる
陽気で親しみやすく、恰幅のよい、
人間味あふれるサンタが登場したのです。
サンタクロースの赤い衣装は、
まるでコカ・コーラを象徴するようですね。
彼の手掛けたイラストは1931年、
雑誌『サタデー・イブニング・ポスト』に広告として掲載されました。
人間味ある温かい雰囲気の新しいサンタは、
人々に受け入れられ、たちまち人気者になりました。
サンドブロムはその後1964年まで、
30年以上にわたり、40点以上の作品を描き続けました。
彼が広告用に描いたイラストは、
ポスター、店頭ポップ、雑誌広告、カレンダー、人形など、
いろんな形で世界に広まっていきました。
それらは現在コレクターズアイテムとして高く評価されているそうです。
コカ・コーラ社はいまも、クリスマスの広告やパッケージなどに
サンドブロム作のサンタクロースを使っています。
クリスマスにコカ・コーラを飲むという習慣は、
このようにしてアメリカで定着していったのです。
サンドブロムは1976年に亡くなりましたが、
彼の描いたバラ色の頬と真っ白な髭をたくわえた、
陽気で優しいなおじいさんは、
いまや全世界の人々が思い浮かべる
サンタクロースのイメージの原型となりました。
以上、コカ・コーラ社のキャンペーンは
このようにして大成功したというお話ですが、
似たような事例ですぐに思い浮かぶのは、
バレンタインデーですね。
本来セントバレンタインデーは、
ローマ皇帝の迫害によって殉教した
聖ウァレンティヌスに由来する記念日です。
当時のローマ帝国皇帝・クラウディウス2世は、
兵士たちの婚姻を禁止しました。
その理由は愛する人を故郷に残したままの者がいると
ほかの兵士たちの士気が下がるというものでした。
司祭ウァレンティヌスは、
婚姻を禁止された兵士たちを憐れみ、
命令に背いて秘密裏に結婚式を行っていましたが、
そのことが皇帝の怒りに触れることとなり、
とうとう処刑されてしまいました。
その日が269年2月14日だったのです。
その後ウァレンティヌス殉教の日に、
若い男女が恋の詩などを匿名で贈り合うという習わしが生まれ、
今日のセントバレンタインデーのもととなりました。
バレンタインデーに
女性が男性にチョコレートをプレゼントするというのは、
日本だけの習慣だそうです。
その仕掛人は〝神戸モロゾフ〟だといわれています。
〝神戸モロゾフ〟は1936年に
日本で初めてバレンタインチョコレートを発売しました。
その後1958年には新宿・伊勢丹で、メリーチョコレート社が
バレンタインセールを行いましたが、
このとき売れたチョコはたった5枚だけ。
たいへんな赤字だったそうです。
バレンタインデーに
チョコを贈る習慣が定着しだしたのは1960年ごろのこと。
当時たいへん人気のあった不二家のハートチョコに対抗するため、
森永製菓が
〝2月14日は愛の日。
ハートのついたカードや手紙にチョコを添えて贈る日です〟と
マスコミを使ってバレンタインデー企画を大々的に展開。
このキャンペーンが切っ掛けで
日本におけるバレンタインデーの習慣が普及していったそうです。
この日ばかりはどんな男も、
麗しい黒髪の乙女がチョコを持って
はにかみながら会いに来てくれるんじゃないかと
あわい期待を抱いたものです。
ちなみにホワイトデーに
チョコのお返しに飴を贈ろうという、
全国飴菓子工業協同組合の思惑は失敗に終わったようです。
さらにちなみに、
自分が子どもだったころはホワイトデーではなく、
この日はマシュマロデーと呼ばれていました。
1977年、福岡のお菓子メーカーである石村萬盛堂が、
チョコのお返しにマシュマロを贈ろうと発案したことが
始まりだったといわれています。
女子たちがバレンタインデーのお返しがないのは不公平だと
話題にしていたことがきっかけで思いついたんだとか。
それじゃあチョコのお返し用お菓子を作ちゃえってことですね。
その後、マシュマロが白かったことからホワイトデーと改名されたようです。
いずれにせよ、熱い想いを告げる習慣が
企業の販促手段の一環だったというのは、
ちょっと寂しい気がしないでもありませんね。
さて、日本独自の習慣といえば、
土用の丑の日に鰻を食べるというものがあります。
この発案者は江戸時代の学者・平賀源内だといわれています。
もともと鰻の旬は秋から冬に掛けてです。
しかも夏場の蒲焼は味が濃すぎて売れにくい。
そこである鰻屋が夏でも鰻が売れる工夫をと、
知恵者である源内先生にアイデアを授かりに伺ったところ、
先生は夏の土用の間で
日の十二支が〝丑〟の日に〝う〟の付くものを食すと縁起が良いという
こじつけとしか思えない妙案を思いつきます。
それに〝精のつく鰻は夏を乗り切るのに最適〟という
セールスポイントを無理やりくっつけて、
鰻屋の店先に「本日土用丑の日」と書いた大きな看板を置かせました。
これが江戸っ子の目にとまり、
なんだなんだと評判になって成功したということです。
でも、定説のように語られるこのお話は、
根拠のないものだともいわれているのでご用心。
さらに節分の恵方巻というのもあります。
恵方巻の発祥は大阪の船場だといわれています。
江戸時代から明治にかけて、
大阪の花街で商家の旦那衆が節分のお祝いや、商売繁盛を祈念して
〝丸かぶり寿司〟あるいは〝太巻き寿司〟を食べたのが始まりだとか。
巻寿司の中には七福にちなんで七種類の具を入れ、
福や運を一気に手に入れるため丸かじりしたそうです。
1932年(昭和7年)には、大阪鮓商組合後援会が、
この風習を世に広めようとしてチラシを作成しています。
1970年代後半頃には、大阪の海苔組合や厚焼組合なども
チラシを作って撒いたようです。
後にこの風習を利用したのが、
高度成長期のスーパーやコンビニでした。
バブル期には豪華で高価な恵方巻が売り出され、
飛ぶように売れたそうですよ。
それでも、平成の初め頃までは、
まだまだ全国的に浸透しているとはいえない状況でした。
最初に〝恵方巻〟という名をつけ全国展開を図ったのは、
コンビニのセブンイレブンだったようですね。
1989年に広島の一部店舗で販売したのがきっかけでした。
2月は催事が乏しく困った関西出身のオーナーが、
そういえば・・・と出身地の習慣を思い出して発案したのだとか。
この目論見は功を奏し、
そのまま一気に全国展開が始まったそうです。
大阪の一部地域の風習だったものが、
いまや全国に知れ渡るようになりました。
節分に恵方巻を食べることが
日本の立派な伝統行事といわれるようになる日も
そう遠くないかもしれませんね。
クリスマスにコカ・コーラ、
バレンタインデーにはチョコレート、
土用の丑に鰻、
節分には恵方巻という習慣は、
うまくいったキャンペーンの代表です。
その一方、なかなか認知されないものもたくさんあります。
代表的なものは語呂合わせで作った記念日ではないでしょうか。
1年365日、毎日がなにかの記念日として制定されていますが、
そのほとんどは一般的に知られていないものが多いようです。
1月10日は〝110番の日〟、
11月9日が〝119番の日〟、
11月22日は〝いい夫婦の日〟なんてまだわかりやすい方ですが、
4月22日は〝良い夫婦の日〟だっていわれたら、
いったいどっちなんだと詰め寄りたくなりますね。
11月23日は〝いい兄さんの日〟らしいのですが、
ここまでいくとなんだそっりゃです。
これらの記念日が定着しないのは、
まずは記念日が多すぎる。
そしてその日が根拠のない単なる語呂合わせである。
ということではないでしょうか。
語られるべき物語やバックボーンがなにひとつありません。
最近は『ブラックフライデー』という言葉を
耳にするようになりましたが、
『プレミアムフライデー』なんていうのもありましたね。
政府と経済界がいっしょになって提唱した
個人消費喚起キャンペーンですが、
『働き方改革』と関連付け、
給与支給日直後に該当しやすい月末金曜日には、
午後3時に仕事を終えて、
夕方を買い物や旅行などに充てることを推奨していました。
でも、この目論見も実情にそぐわない感じで定着しませんでした。
〝20日、30日は5%オフ♫〟のイオン〝お客様感謝デー〟や
31日は〝サーティーワンの日〟などは、
宣伝効果がうまく発揮された良い例だと思います。
クリスマスにコカ・コーラ、
バレンタインデーにはチョコレート、
土用の丑に鰻、
節分には恵方巻のように
キャンペーンを成功させるのは容易ではありません。
でも、だからといって
できないことではありません。
古来からある伝統や習慣、
伝説や物語とうまく組み合わせることも、
成功させるカギのひとつといえるのではないでしょうか。
過去の成功事例にしがみついていてはいけないと言われたりしますが、
故きを温ね新しきを知るとも申します。
流行は20年周期で繰り返すともいわれますね。
昔のことを研究し、
そこから新しい知識や道理を発見することもだいじなことだと、
いまさらながらしみじみ思うきょうこのごろです。
W・M