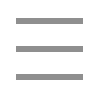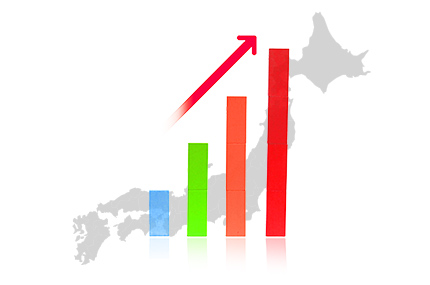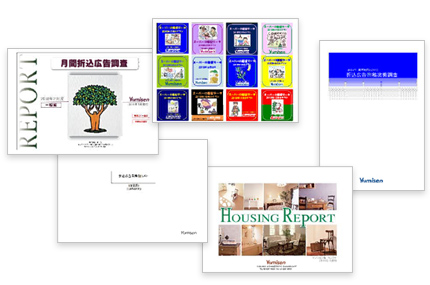突然ですが、
外国の人に〝わびさび〟の意味について尋ねられたら、
あなたはちゃんと説明できますか?
〝わびさび〟は英語でもWabi-Sabiと表します。
日本文化を紹介するとき、
代名詞のように用いられる言葉のひとつでもありますね。
けれど、茶の湯などをたしなんでいる人ならともかく、
ふつうは答えられませんよねぇ。
多くのひとはただぼんやりと、
なんとなくわかったような気になっているだけじゃありません?
で、〝わびさび〟について調べてみました。
〝わびさび〟を漢字で表すと〝詫び寂び〟となります。
〝詫び〟と〝寂び〟は一緒くたにされがちですが、
実はふたつの意味は異なるんだそうです。
〝詫び〟の意味を調べてみると、
わびしいこと。思いわずらうこと、悲しみなげくこと、
落ち着いて、静かで質素な趣。閑寂・・・とありました。
もともとは、思うことがかなわず
悲しみ、思いわずらうことという意味でしたが、
室町時代あたりから、自分の思い通りにならない状態を受け入れ、
積極的に安住しようとする肯定的な意味をもつようになったそうです。
一方、〝寂び〟の意味するところは、
現象としての渋さと、それにまつわる寂しさとの複合美。
無常観や孤独感を背景とした、日本古典芸術の代表的な美のひとつ
・・・ということだそうです。
そういわれてもよくわかりませんが、つまり、
この世のあらゆるものは、寂びれたり、汚れたり、欠けたりします。
それは一般的には劣化とみなされますが、
その変化の織りなす、多様で独特な美しさを〝寂び〟と呼ぶようです。
精神性を表現した〝侘び〟とは違って、
〝寂び〟は内面的な本質が表面的にあらわれていく
その変化を美と捉える概念のようです。
〝寂び〟は見た目の美しさについての言葉ですが、
〝詫び〟は寂びれや汚れを受け入れ、楽しもうとする
前向きな心についての言葉なんですね。
〝寂び〟の美しさを見出す心が〝詫び〟というわけです。
閑寂、清澄、枯淡の境地、
もの静かでどことなく寂しげな、
あるいは色彩感を否定したような枯れた趣、
このような否定的な感情をあらわす言葉を、
逆に美を表すものとして
茶の湯や俳諧などの文芸の世界で用いるところに、
日本独自の美意識があるといえそうです。
日本の美意識は、西洋文化のように
論理的には説明できないものだといわれます。
言葉にならない美を表現するため、
その周辺にある
さまざまなものの様子を切り取って置き換える。
そんな感性が、日本では伝統的に育まれてきました。
良く知られるところでは松尾芭蕉の句がありますね。
〝古池や蛙飛び込む水の音〟
〝閑さや岩にしみ入る蝉の声〟
〝蓑虫の音を聞きに来よ草の庵〟
華やかさが流行りだった俳句の世界において、
詫び寂びを織り込んだこれらの句は、
当時の俳人たちには、かなり大きな衝撃だったようですよ。
〝詫び寂び〟という言葉が、
美を感じさせる言葉に変化していくのには、
その背景として和歌文学の伝統があったそうです。
平安時代から鎌倉時代に至る和歌的世界で、
閑寂・簡素・枯淡の境地が生み出されたみたいですね。
このような深みのある独特な美意識こそ、
ほんとうのクールジャパンなんじゃないかと思うのですが
いかがでしょう?
さて、みなさんの仕事において
〝わびさび〟のようにうまく説明できない事柄はありませんか?
自分にとって、自分たちにとって、会社にとって、
それぞれの業界にとってはあたりまえのことでも、
お取引先や一般の生活者にとっては馴染みがない、
わけが分からないってことありそうです。
そんなときわかりやすく説明できるでしょうか?
うまく説明できないこと、
あたりまえだと思い込んであえて説明してこなかったことが、
実は自分たちの〝強み〟だったりすることがあります。
外部環境や競合の状況から
事業の成功要因を導き出す方法として、
3C分析というものが使われます。
3Cとはご承知のように、
customer(市場・顧客)
competitor(競合他社)
company(自社)のことですね。
この3Cをよく理解することが
とても大切なんだと、
誰もがわかっているはずです。
でも自社のこととなるとどうでしょう?
お客様や、競合他社のことはともかく、
自社のこととなると、
わかっていそうで
実はよくわかっていないということがありそうです。
縦割りの組織だとなおさらですね。
他部署がなにをやっているのか、
どんなことに取り組んでいるのか、
なにを考えているのかさえ、
知らないことがあるんじゃないでしょうか?
あらためて考えてみる、調べてみるということも、
あまりしないような気がします。
たしかに自社のことは、
知っていてあたりまえ、
あらためて調べる必要もないと思いがちです。
また、自社の強みだと主張していたものが、
よくよく調べてみると実は違ったなんてこともあります。
例えば、「自社の強みはフットワークの軽さ」や
「きめ細かいサービスです」と胸を張ったところで、
そんなのはあたりまえのことです。
お取引をする以上、求められてしかるべきものですね。
あるいは、「自社の強みは技術力です」といった場合も、
実は設備投資をして
高性能の機械を有しているというだけなのかもしれません。
その高性能の機械が
お客様にとって必要かどうかは別問題ですね。
そもそもそのようなことさえも、
自社より他社のほうが優れていて、
強みでもなんでもなかったなんてことがあるかもしれません。
反対に自分たちにとってはあたりまえで、
いまさらアピールするべきほどのことじゃない
そんなの強みでもなんでもないと思っていることが、
実は他社には真似することのできない、
しかもお客様にとって魅力的なことだったなんてことも
ないとは言い切れません。
では、自社の強みって何でしょう?
強みを見つけるって意外と難しいものです。
そこで、あえて強みを見つけるのではなく、
基準や平均から大きくかけ離れたものに
注目してみてはいかがでしょう?
自分たちにとってあたりまえなことは、
なかなか気づきにくいものです。
ですからなにか基準、平均となるものと比べて、
プラスかマイナスのどちらかに
大きくはみ出したものに注目して可視化してみるのです。
もちろんプラス側に大きく振れている事柄は
自社の強みになり得ますし、
マイナス側に大きくかけ離れたことも、
強みに変換できる可能性があります。
プラスもマイナスも自社の特徴として捉えてみましょう。
マイナスがプラスになるわけないじゃんと
思う方もいらっしゃるかもしれません。
でも、そのような成功事例はたくさんありますね。
岩手県の葛巻(くずまき)町の例もそのひとつです。
中部岩手県中部に位置する岩手郡の中にあるこの町は、
町というよりも村です。
北緯40度に位置し、面積は約435㎢、
町の面積の97%が標高400メートル以上の高地で、
86%が森林、周囲は1,000mを超える山々に囲まれた山村。
1960年に16,000人いた人口は、
2020年住民基本台帳によると5,092人、
世帯数は2,708世帯まで減少してしまいました。
町にいる牛の数は1万数千頭で、
人より牛の数の方がはるかに多く、
しかも高齢者比率が極めて高い典型的な過疎地です。
さらに、観光資源がまったくありません。
駅がない、インターチェンジがない、
温泉も、スキー場も、ゴルフ場もない。
牧場比率は町の総面積の3.2%で、
5.8%ある原野の方が広いという、
ないないづくしの超田舎町です。
これだけなんにもない場所で、
なにかしようなんて思いつかない、
なにもできないお手上げ状態・・・と
あきらめてしまうのが普通です。
でも、葛巻の人たちは違いました。
このなにもないというマイナスの環境を、
プラスに転じることに成功したのです。
地方でありがちなのは、
『都会志向』『名物思考』といわれるものです。
使いもしない道路や橋を作ったり、大きなホールを建設したり、
無理やり名物や特産品をでっちあげたりして、
その結果、
さらに経済沈下を起こしてしまうというのは
なんとも残念な地方あるあるですね。
ところが葛巻ではあえてその逆をいきました。
徹底的にローカルを極めたのです。
いつかは都会のようにではなく、
ローカルをこれでもかと深掘りし、
ローカル要素を活かしきることに注力したのです。
葛巻は高地にあるため、たいへん強い風が吹きます。
この風は、牧場の柵を倒したりして、
昔から厄介者扱いされていたそうです。
迷惑きわまりない強風は
一般的にはマイナス要素と捉えられがちですが、
葛巻の人たちはこれを何かに利用できないかと考えました。
そして、しぼり出した答えが風力発電でした。
風力発電の損益分岐点は、
風速毎秒6mと言われていますが、
葛巻では8mもの風が吹くそうです。
そこで高原の尾根沿いに12機のプロペラを設置し、
年間5,400万キロワットの電気を作り出すことに成功したのです。
これは16,000世帯に1年分の電力を供給できる量でした。
葛巻の世帯数を考えると、数年分の電力が賄えることになります。
1キロワット時10円で売っても、収入は5億4,000万円ですね。
また、人よりも牛の数が多いといわれる土地柄を活かして、
子牛の保育園ビジネスをはじめました。
これは全国の酪農家から仔牛を預かって、たいせつに育て、
お産をする2か月前にお返しするという事業だそうです。
葛巻の仔牛保育園で育った牛は、
農林大臣賞をはじめとする数々のコンテストで優勝するなど
実績を積み重ねました。
いまではブランド牛を育てるなら葛巻‼
といわれるほどの名門仔牛保育園となって、
年商数億円の事業にまで成長しているそうです。
そのほかにも、太陽光発電、
家畜の糞尿を利用したバイオマス発電、
牛乳やワインの生産などの施策を次々に打ち出しました。
牛乳やワインは葛巻町の産地限定ブランドとなっています。
その結果、葛巻町は年間数億円の黒字を出し、
これらの実績を耳にした人たちが、
毎年全国から数十万人も視察に訪れるまでになったそうです。
現在この町のキャッチフレーズは、
「北緯40度 ミルクとワインとクリーンエネルギーのまち・葛巻町」
となっています。
葛巻町はなんにもない田舎町という、
マイナス側に大きく振れた針を、
みごと強みに変換しました。
〝わびさび〟だって、
マイナス要素をプラスに変換したものです。
〝わびさび〟は欧米文化にない思想です。
だからこそ興味をもたれます。
でも、わたしたち日本人にとっては、
血に刷り込まれている感性、
あたりまえすぎてあらためて考えてみることのないものです。
自社の〝強み〟についても同じことが言えるかもしれません。
企業やそこで働く人々が
往々にして陥りがちなのは、
自分たちの製品、自分たちのサービスから、
ものごとを発想してしまうということ。
それでは基準、平均となるものと比べて、
プラスかマイナスのどちらかに
大きくはみ出したものに気づくのは難しいかもしれません。
自社の強みを見出すのにも苦労しそうです。
どんなに成熟した市場にも、
ビジネスチャンスは必ずあるといわれます。
〝宝の持ち腐れ〟にならないよう、
いまいちど周りを見直してみてはいかがでしょうか。
W・M