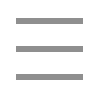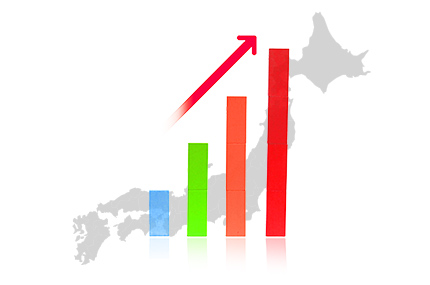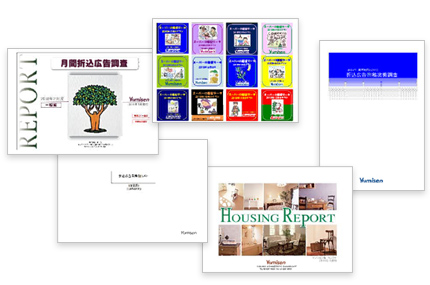10回クイズってご存じしょうか?
代表的な例をあげれば、
質問者が「ピザって10回言ってみて」といい、
回答者に連続して「ピザ」と10回言わせます。
言い終わったらすぐに質問者が自分の〝ひじ〟を指差して
「ここはなに?」と質問し、
回答者が間違って〝ひざ〟と答えると
「バーカ、ここは〝ひじ〟ですよぉだ。やーい、やーい」
というちょっと意地悪な遊びです。
実はこのクイズ
1987年に放送されたニッポン放送のラジオ番組
〝オールナイトニッポン〟が起源だといわれています。
他にはこんなのもありましたね。
「シャンデリアって10回言ってごらん」
「シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア……」
「毒リンゴを食べたお姫様は?」
「シンデレラ!」
「ブッブー、正解は白雪姫でしたぁ。ケケケッ」
これは同じ言葉を何度も繰り返すことで
「シャンデリア」という単語が頭の中にインプットされ、
質問の内容から瞬間的に童話と結びつき、
無意識に連想されたワードが
咄嗟にアウトプットされた結果です。
興味深いのは
この種のひっかけ問題は、
幼い子供には効果がないということです。
10回クイズの大事な要素は、
ワードの音が似ていて、
何らかの関連性があり、
またキーワードが身近な単語で、
意味を深く考えなくても
口をついて出てくるということです。
簡単に連続して言えるワードで
頭の中が一杯になったところに質問をすると、
音が似ている関連性のあるワードを
素早く連想してしまって、
疑いもなくつい答えてしまうという仕組みですね。
わたしたちは連想したり、予想したりすることで
作業の効率化や問題解決を図ろうとします。
それは無意識に行われることが多々あります。
たとえば運転中に見通しのわるい交差点にさしかかると、
もしかすると子供や自転車が飛び出してくるかも・・・
と思って警戒し足が自然にブレーキペダルに触れますね。
でも、幼い子供たちは
言語能力や知識の蓄積が不足しているので、
過去の出来事から連想して
先のことを予想するという能力が充分ではありません。
連想する能力が無いというわけではなく、
無意識下でそうすることが出来ないのですね。
つまり無意識に次に起こりそうなことを
予想あるいは連想して行動する大人は
10回クイズに引っ掛かりやすく、
そうでない幼子は
引っ掛かりにくいということです。
ある実験をご紹介します。
被験者にちょっとした肉体労働をしてもらう前に、
Aグループには、作業後のご褒美となるであろう
おやつやドリンクなどを、
なにげなくチラリと見せておきます。
そしてBグループには、
何も見せないですぐに力仕事をしてもらいます。
その結果、
Aグループの方が最後まで忍耐強く作業を続けたそうです。
また、ビスケットやクッキー、
ミルフィーユやクラッカーなど、
ぽろぽろとこぼれやすい食べ物を、
A)かすかに洗剤の香りのする部屋で食べてもらう
B)なんの匂いもしない無臭の部屋で食べてもらう
そうすると
食後にテーブルの上をきれいにする人が、
Bグループに比べてAグループは、
3倍ほど多かったそうです。
これらの実験の共通点は、
被験者になぜそうしたのか、そうなったかと質問しても、
自覚がないので、ただなんとなく…としか
答えられないということなんだそうです。
事程左様に
わたしたちは自分の中の〝無意識〟に操られやすいのです。
なんとなく見聞きしたことが記憶に残り、
なにかの拍子にその記憶のカケラが呼び水となって、
つい行動に移してしまうのですね。
このように事前に見聞きしたことが
その後の判断や行動に影響を与えることを
プライミング効果といいます。
皆さんの身のまわりにも
なんでこんなもの買っちゃったのかなぁ・・・
なんてものがいろいろありませんか?
どうやらわたしたちの行動のかなりの部分が、
なんらかの刺激をきっかけとした
無意識の連想でできあがっていそうですね。
・・・後編につづく・・・
W・M