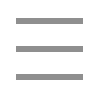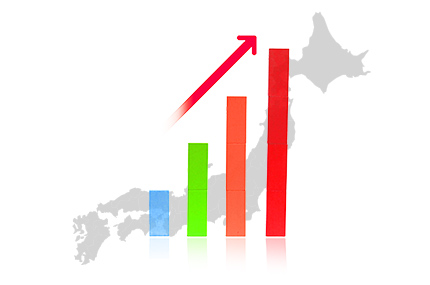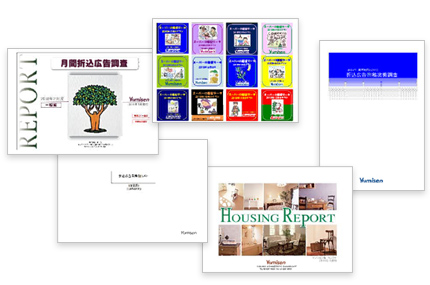スーパーをはじめとする小売量販店の開店情報を収集していると、小型スーパーが増えているように感じる。そこで、気になった企業を取り上げてみた。
1社目は、ディスカウントスーパーのサンディだ。近畿2府4県の183店に加え、東京・埼玉・三重・岡山に9店舗展開している(2021年12月末時点)。2017年6店、2018年9店、2019年10店、2020年5店、2021年16店と、コンスタントに出店している(近畿圏・読宣調べ) 。2020年はコロナの影響か出店を控えていたようだが、2021年は出店ペースも上がっており、年後半はリニューアルや移転を積極的に行い、集客力を高めている。コンビニ2つ分ほどの広さの店舗が多く、マンションの1階や閉店したスーパーの居抜き物件への出店も多いので、開店準備の日数が抑えられている。(※参考 コンビニの売場面積約130~200㎡)
サンディの特徴と言えば、レジ袋の有料化は義務化される前から実施しており、ダンボール陳列によるコストカット、そしてレジ付近に自由に使えるダンボールが置かれているのが印象的であった。食料品だけでなく、ティッシュや消毒液なども販売してあり、近所にあると嬉しい店舗の一つと言える。
折込チラシは黄色紙で黒一色、すぐにサンディとわかる仕様だ。コロナ前は週2回折込をしていたのが、一気に自粛した。最近は、たまに目にするようになったが、早くコロナ前のように戻って欲しいと願う。
余談だが、2020年12月3日のサンディ今里店までは木曜日オープンであったが、鶴見緑店以降は土曜日オープンに変更している。鶴見緑店も当初、HPには12月10日(木)オープンで告知していたのが12日に変更したように記憶している。折込を自粛して、従来の投函日である木曜日を意識しなくてよくなったからか、それとも11月24日にオープンしたロピア鶴見島忠ホームズ店が影響したのかと勘繰ってしまった。
2社目はライフコーポレーションだ。ライフやセントラルスクエアのほかに、Miniel(ミニエル)やBIO-RAL(ビオラル)といった屋号の店舗を出店している。Minielは、ホームセンターコーナン西本町店の一角に251㎡で構えており、周辺はオフィスも多いこともありコンビニのような感覚で利用されている。
一方、BIO-RALはオーガニック商品を中心に食品だけでなくスキンケア商品なども販売しており、昨今のオーガニック志向を反映した店づくりだ。1号店は、2016年6月にライフ靭店の店名を変更してオープンし、2021年10月にはJR大阪駅のエキマルシェ内にオープンしている。関西には、まだ2店舗しかないが、既存の一部のライフでもBIO-RAL商品を展開しているので、チェックする価値はある。
最後は、ダイエーが展開するCoDeli(コデリ)。大阪市内でも都市部への出店攻勢で、1号店は2020年11月にオープンした南堀江2丁目店で、堀江公園からほど近い場所にある。2021年12月末で9店舗となり、2022年1月はすでに3店出店している。出店地は都市部のマンションの多いエリアで、売場面積は150〜200㎡前後でイオンエクスプレスやコンビニ跡地の出店も多い。
生鮮食品は、野菜と肉が少し陳列しているが、鮮魚はなく、惣菜や冷凍食品を中心にラインナップしており、ほぼコンビニと言っていいだろう。ジュースなどのナショナルブランドは定価販売ではないので、コンビニで買うよりは安く買える。入口すぐに弁当・惣菜を陳列しているのが、CoDeliのフォーマットとなっていそうだ。
これらの企業が小型店舗で積極的に出店する背景には、高齢化と少子化があると考察した。
ロードサイドにあった大型スーパー(GMS)は、衣料品や家電、生活雑貨を扱っていたが食品スーパーへと業態を変えてきている。食料品だけに特化し、衣料品やドラッグ、家電は専門店にテナントとして入ってもらう形態だ。イズミヤ高野店・古市店・小林店は、自前の売場を縮小してホームセンターコーナンを誘致している。ネット通販の拡大もあるが、衣料品やドラッグストアなどの専門店の台頭は、大型スーパーに大きな変革を迫ったと言える。
大型スーパーの方が経営効率は良さそうなイメージはあったが、高齢化が進むと行動範囲が狭くなるので、小型店舗でも近所にあると重宝する。買い物難民対策として、移動スーパーのとくし丸を扱うスーパーも増えてきている。徒歩圏に買い物施設がない地域では、来店するのも一苦労だ。とくし丸、ネットスーパー、配達サービスと、企業も売上確保で必死だが、今後を見据えた取り組みで、スタッフとの会話も生まれ、お年寄りの見守りの意義もありとても良いと思う。
少子化・人口減少による働き手不足対策として、新規出店するスーパーのほとんどで採用しているのが、完全セルフレジや精算専用レジである。非接触や待ち時間短縮と消費者にとってもメリットは大きい。サンディも新店だけでなく、既存店にも精算専用レジを導入してきている。
イオンやダイエーは、セルフ・精算レジに加え、レジゴーというスマホの大きさの端末でレジの待ち時間を無くす工夫をしている。レジゴーを設置しているイオンフードスタイル茨木太田店で試してみた。操作は至って簡単だ。専用端末で商品のバーコードをスキャンして買い物カゴに入れ、専用のレジレーンで会計をするだけで、レジ列と商品のスキャン時間を待たずに買い物が終えることができる。しかし、この店舗では使用する人はそこまで多くなかった。レジゴーを導入したことで、これまでの有人レジとセルフレジの台数が減ったのでレジゴーを利用しない人にとっては長蛇の列になっている。店舗の端末を使わずに自分のスマホにアプリもインストールできるので、少量で買うものが決まっている人にはレジゴーがオススメだ。
同様の施策をトライアルカンパニーでもレジカートというサービスで導入しているようだが、まだ関西の店舗では展開していないようだ(読宣調べ)。
また、業務スーパー天下茶屋駅前店ではタブレット付きのカートや店内のAIカメラによる解析で、欠品による販売機会の損失を防ぐ効果もある。消費動向を把握して運営効率を図っているが、欠品が少なくなれば消費者にとってもメリットは大きいと言える。
コロナによる生活様式の変化は、我々にもっとも身近な「食」に多大な影響を与えている。外食から中食へ、大型店舗から小型店舗へ、食料品を扱うスーパーやドラッグストアの存在はますます大きくなると感じている。少子・高齢化を乗り越える方策として、ITやAIを活用する事が普通と言われる未来はすぐそこまできていると感じた。
智